| テーマ | ~薬を正しく知るために~ |
|---|---|
| 内容 | 薬は「ドラッグ」とも「メディスン」(Medicine)とも呼ばれる。古代は、経験則に基づいて、植物や鉱物を医薬として用いて医療をしていた。そして、毒薬もしかりである。当然のことながら、必ずしも科学的な証拠(Evidence-based)に基づいたものではなかった。 しかし、科学の発展とともにだんだんに変化し、今では創薬は科学的なプロセスに基づいてなされている。ただし、そのときに忘れてはいけないのは、倫理性である。薬事承認には、治験をすることが必要である。治験はGCP (good clinical practice)の規制下に行われ、科学性のみならず倫理性が強く求められる。また、国(厚労省など)の適切な規制と迅速な対応もきわめて重要である。我が国では、これが機能しなかったために、いくつもの「薬害」が起こっている。また、昨今では「ディオバン事件」などの研究不正問題も起こっていることも忘れてはならない。薬は、逆から読めばリスクである。薬には完全なものはない。薬とは、常にベネフィットとリスクの両面性を持ち合わせている。このため、「薬は毒にもなりうる」。 日本では、薬信仰なる盲目的な考えがあると同時に、薬に対する(あるいは医療に対する)不信感もある。このように二面性を持つ薬をどのように使用するかは、医師の「腕」にかかっている。また、「さじ加減」は単なる勘ではなく、科学的根拠に基づく必要がある。薬剤師は、これを検証すると同時に、患者に対して啓発活動をすることが求められる。さらに、患者みずからが薬のベネフィットとリスクを理解する必要がある。 本講演では、1)薬ができるまでのプロセス、2)治験の実際、3)薬事承認と保険収載、4)副作用のメカニズムとリスクマネジメント、5)薬害の実態、6)副作用が出た際の健康被害救済法、などについてわかりやすく解説をしたい。 |
| 開催日 | 2018年1月19日(金) |
| 場所 | お茶の水医学会館9F |
| 講師名 |
 本学名誉教授 本学名誉教授宮坂 信之(医21・昭48卒) |
| 略歴 | 1973年 東京医科歯科大学医学部卒業、第一内科入局 1979年 カリフォルニア大学医学部サンフランシスコ校Postdoctoral Fellow 1982年 テキサス大学医学部サンアントニオ校内科研究部門助教授 1986年 東京女子医科大学リウマチ痛風センター内科助教授 1989年 東京医科歯科大学難治疾患研究所教授 1995年 東京医科歯科大学医学部第一内科教授 2000年 東京医科歯科大学医学部膠原病・リウマチ内科教授(大学院改組のため) 2010年 東京医科歯科大学医学部附属病院長 2012年 東京医科歯科大学名誉教授 現在:医薬品医療機器総合機構(PMDA)専門委員、日本医療研究開発機構(AMED)プログラムオフィサー、厚生労働省先進医療会議座長、日本学術会議会員、千葉大学経営協議会委員など |
| プログラム | ○19:00~20:15 講演会・質疑応答 ○20:15~21:00 懇親会 |
| 会費 | 1,000円 |
| 定員 | 50名 ※定員になり次第受付終了 |
| 対象者 | 同窓会員、会員家族、大学関係者、本学学生、一般の方 |
| 問い合わせ先 | 一般社団法人 東京医科歯科大学医科同窓会(イベント企画委員会) 担当:苅込志乃 karikomi TEL:03-5689-2228 FAX:03-5689-2229 E-mail:ikadoso@ikadoso-tmdu.jp |
| 申込み締切 | 2017年12月27日(水) |
| 備考 | チラシ➡第12回フォーラム |
第12回講演会 薬はリスク?【講師:宮坂信之】
2018年1月19日(金)開催!
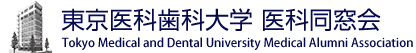



 Instagram
Instagram
 Facebook
Facebook